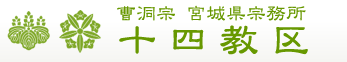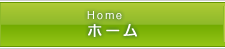南無釈迦牟尼仏
仏教を開いたのは「シャカムニ」である。聞き慣れない言葉ではあるが、漢字に直すとこうなる。
「釈迦牟尼」〜 いわゆるお釈迦様である。
いまから二千五百年ほど前…
紀元前四六三年(他に紀元前五五六年等諸説あり)四月八日、インドのカピラ国に王子がお生まれになった。その父である国王はシッダールダという名をつけて祝ったと伝えられる。
このカピラ国はシャカ国ともいわれていた。
「シャカ」とは種族の名前である。
王子は成長するにつれ、人間として避けることのできない「生・老・病・死」といった問題や、人間社会の不合理な階級制度に対しての悩みが深くなっていった。そして二十九歳の時、当時の慣習にしたがって、一修行者となって苦行林への道に向かうことを決心した。
バラモン教の苦行を六 年間も続けた王子は、すっかりやせ衰えてしまった。しかしながら、王子はこの方法では決して安心解脱は得られないとさとり、苦行をやめることにした。そして、現在パルグ河と呼ばれている河で、その流れに身を浄め、ウルヴェーラー村のスジャーターという娘から乳粥の供養を受け、元気を回復した。
元気になった王子は、ブッダガヤー(ボードガヤー)という地にて、菩提樹(ピッパラ)の下に草を敷いて”坐禅の行“にはいった。
〜王位を捨て、家族を捨て、六年間、さまざまな苦行を続けてきた。それは、精神を統一したり、身心の苦痛に耐える手段とはなっても、深い深い精神的苦悩の解決にはならなかった。快楽にふけり楽しむ生活が一方の極端だとすれば、苦行はもう一方の極端ではないか。〜
この”坐禅の行=禅定“にはいって八日目、王子三十五歳の十二月八日、暁近いころ、すべての迷いや悩みが滅して、さとりを開き、”真理を悟った人=仏・仏陀“となった。
初めに示した「シヤカムニ」の「ムニ」とは「聖者」という意味なので、曹洞宗のご本尊である釈迦牟尼仏とは次のようになる。
読み シャカ ムニ ブッダ(ブツ)
(漢字をあてはめて)
音写 釈迦 牟尼 仏陀(仏)
意味 釈迦族の 聖者たる 真理を悟った人
なお、南無とは、「敬意を表すために体を折り曲げること、帰依」という意味である。
さて、十二月八日は、お釈迦様がさとりをひらかれた日として、「成道会」という法会を営んでいる。成道とは「仏の修行の完成・悟りを開く」という意味である。また、「会」という漢字は、仏教では「え」と読むことが多い。意味はもちろん「あう・であう」だが、その他にも「かなう・あわせる・あつまり」などという意味がある。
仏教の行事は普通「◯◯会」と言い表され、つまり「成道会」と言えば、お釈迦様が悟りを開かれた記念の日という意味合いと同時に、その記念の行事に「出会う」「集まる」ということにもなるのである。
先に「十二月八日、暁近いころ、すべての迷いや悩みが滅して、さとりをひらき、”真理を悟った人=仏・仏陀“となった」と説明したが、さて、では何をさとったのか。ひとことで言えば「世の中は縁起している」ということである。
「縁起」とは「縁りて起こる」ということである。
あらゆるものごとは、他と関係なしに単独で存在するものはなく、必ずいろいろな原因や条件によって成立しているということで、すなわち相互依存の世界をいいあらわしている。そのような縁起の世界では、どのような現象や存在も永遠不滅なものはなく、たえず変化をくり返しているということなのである。
さて、そのことをさとられたお釈迦様は、どのような「法=教え・真理」を説かれたのか。以下、『ダンマパダ(法句経)』(岩波文庫「ブッタの真理のことば・感興のことば」)より挙げてみる。
「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしもよごれた心で話したり行なったりするならば、苦しみはその人につき従う。車をひく(牛の)足跡に車輪がついて行くように。」
「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも清らかな心で話したり行なったりするならば、福楽はその人につき従う。影がそのからだから離れないように。」
「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永遠の真理である。」
「他人の過失は見やすけれども、自己の過失は見がたい。ひとは他人の過失を籾殻のように吹き散らす。しかし自分の過失は、隠してしまう。狡猾な賭博師が不利な骰の目をかくしてしまうように。」
「他人の過失を探し求め、つねに怒りたける人は、煩悩の汚れが増大する。かれは煩悩の汚れの消滅から遠く隔っている。」
「煩悩」=心身を乱し悩ませ、正しい判断をさまたげる心のはたらき。貪(むさぼり)・瞋(いかり)・癡(物事の正しい道理=すべて固定的なものはなく、縁起しているということ=を知らないこと)の三毒といわれるものが、煩悩の根源的なものといわれる。煩悩は、自己中心の考え、それにもとづく事物への執着から生ずるという。ちなみに、除夜の鐘は百八つ。百八の煩悩があるともいい、それらを除く意味を込めて百八回つくとされる。また、百八の数は一年(十二月・二十四節気・七十二候の数の総計)を意味するともいう。
さとりをひらいたお釈迦様は、その後四十五年間、ガンジス河中流地域を中心に布教の旅を続けたという。その間にお弟子さんは次第に増え、また、竹林精舎(最初の仏教寺院。精舎とは僧侶の居住する建物のことで、竹林を寄進され、伽藍=「建物」をその場所に建立されたことによりこの名前でよばれる)・祇園精舎(この精舎で、お釈迦様は多くの説法をしたという)なども建立され、教団の組織もしだいにととのっていった。
そして、お釈迦様はクシナガラというところで、沙羅双樹のもとに身を横たえ最後の説法をし、その生涯を閉じたとつたえられる。紀元前三八三年(紀元前四七六年等諸説あり)二月十五日のことである。
この二月十五日は「涅槃会」と呼ばれ、十二月八日の「成道会」、そしてお釈迦様が生まれた四月八日の「仏誕会(花祭り)」とともに「三仏忌」の一つとなっている。
なお、「涅槃」とは、生命の火が吹き消されたということで、入滅(死去)という意味と、煩悩の火が吹き消された状態の、安らぎ、さとりの境地という意味として使われている。
お釈迦様の時代から今日まで変わらずに、仏教をつらぬいているものは、「仏法僧の三宝」を敬うということである。「三宝=三つの宝」とは、悟りを開いた「仏」と、その教えである「法(お経 )」と、それを奉ずる人々である「僧」のことをいう。
そして、仏教の歴史とは、お釈迦様の教えを学び、それを人々に伝えようとした、人間の歴史ということもできる。