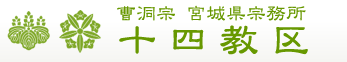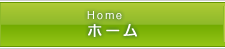開山・沿革・建造物
所在地・登米町日根牛
当寺は、天正十年(一五八二年)現在の白石市内に吉州壽琢大和尚によって開山された。
吉州壽琢大和尚は、白石、養雲寺六世住持の職を退董し、庵をむすび玉秀寺を開山し翌々年の天正十二年九月十一日示寂されている。
吉州壽琢大和尚の示寂後は、法灯が途絶えたが百十六年後の元禄十三年(一七〇〇年)、二世光厳鏡尊大和尚によって現在地に再興された。
この時代、寺社法度によりみだりに新寺の建立が禁止されていたために古寺復興の形式をとったものと考えられる。
登米藩史稿には、元禄十三年「この年養雲寺先見和尚、米谷山玉秀寺を再興す」と記載されており、玉秀寺墓地入り口にある阿弥陀石仏供養塔には、元禄十三年導師光厳と刻まれており、先見和尚とは二世光厳鏡尊大和尚のことである。
日根牛には、葛西氏の時代に小泉伊豆という家臣が小池館におり、その小泉氏の牌所らしい仏堂が現在地にあったのだろうと考えられる。
また、玉秀寺墓地には慶安元年(一六四八年)開山の真言宗蔵福院(明治三年廃寺)開山和尚の供養塔があることなどから、古くからの当地域の蘭場であったことが推察される。
享保五年(一七二〇年)登米藩主伊達村永公より、畑代五十文の地を寄進され日根牛地域の菩提寺としての基礎が築かれた。
その後、慶応二年(一八六六年)寺池金谷から出火した火の粉が、北上川を越えて当寺にも飛び火し全焼した。そのとき本尊、脇仏の三体と過去帳および若干の什物を持ち出しただけで、他はすべて消失し、詳細な記録は全く解らなくなった。
火災後に庫裡を建て、更に明治二十二年(一八八九年)小規模な仮本堂を建立した。
昭和九年(一九三四年)境内にあった登米小学校日根牛分教場が移転したあと、本堂を再建することになったが資金に不都合が生じ、建築規模を縮小して建立したのが現在の本堂である。
昭和五十三年(一九七八年)龍源寺三十世俊渓雄道大和尚が、当寺の兼務住職となるや損傷の甚だしい庫裡や手狭な本堂の増改築と開山堂の新築、境内整備、その全般にわたる再興を発願し檀信徒の一致協力により、大改修がなされ昭和六十年(一九八五年)盛大に落慶式を修行した。その後も、参道の整備や直歳寮倉庫の改築と黒門の新築、庭園の整備がおこなわれ面目を一新した。
さらに、平成に入り現住職になってからは寺務所、書庫、干支地蔵堂、真量閣、本堂を新築し、特に干支地蔵堂は近年珍しい地場産品のスレート茸で建立した。教化活動では、梅花講、写経会、仏教青年会を組織し、寺報の発行とあわせ檀信徒のニーズに応えた活動を行っている。なお、これらの教化活動により、曹洞宗認可参禅道場の認可を受けている。
現在最古の建造物は山門であるが、建立年は不明である。
本尊・仏像・仏画
| (本尊) | 釈迦牟尼仏(元禄ごろの作) |
| (脇仏) | 文殊菩薩、普賢菩薩(元禄ごろの作) |
| (仏像) | 開山大和尚像、承陽大師像、常済大師像、僧形文殊像、達磨大師像、 大権菩薩像、韋駄尊天尊像、ウスサマ明王像、他数点 |
| (石仏) | 十二支地蔵、他、当地方では珍しい双対石仏多数(江戸期) |
| (仏画) | 涅槃図(明治初期)他、多数 |
本寺・歴代住職
| 本寺 長禄寺(福島県・須賀川市) | ||
| 開山 | 吉州壽琢大和尚 | 天正十二年示寂 |
| 二世 | 光厳鏡尊大和尚 | |
| 三世 | 月洞祖寒大和尚 | 延享四年示寂 |
| 四世 | 龍嶽瑞泉大和尚 | |
| 五世 | 老山潜牛大和尚 | |
| 六世 | 空巌宅心大和尚 | 報恩寺、普慶院より転住 元文三年示寂 |
| 七世 | 安国牧山大和尚 | 延享二年示寂 |
| 八世 | 南庭大蟲大和尚 | 宝暦三年示寂 |
| 九世 | 堤宗舜全大和尚 | 天明四年示寂 |
| 十世 | 宗雪徹俊大和尚 | |
| 十一世 | 東峰恵昊大和尚 | |
| 十二世 | 天桂儀範大和尚 | |
| 十三世 | 活道百歩大和尚 | 龍源寺へ転住 文政七年示寂 |
| 十四世 | 潭室春鱗大和尚 | 龍源寺へ転住 嘉永三年示寂 |
| 十五世 | 一智春暁大和尚 | |
| 十六世 | 學田萬龍大和尚 | |
| 十七世 | 泰山天鱗大和尚 | |
| 十八世 | 大光隆道大和尚 | 陽山寺へ転住 明治六年示寂 |
| 十九世 | 雲山真隆大和尚 | 陽山寺より転住 |
| 二十世 | 雪羽秀禅大和尚(関川) | 崇徳寺より転住 大正十一年示寂 |
| 二十一世 | 雪厳碩宗大和尚(高平) | 昭和五十三年示寂 |
| 前住 | 俊渓雄道大和尚(佐竹) | 龍源寺三十世 |
| 現住 | 俊海孝喜(佐竹) | |
寺宝・文化財
| 本山木版刷り「正法眼蔵」全巻、寛政の殿鐘、文化の青銅花瓶、旅の芭蕉像、 版木数十点、月舟宗胡の書、歴代本山禅師の墨筆多数、書画多数、他 |
教化事業・行事
| (年分行事) | 一月一日修正会、一月どんと祭、二月涅槃会、四月花祭り、 八月十二日盆供養会、十二月成道会 |
| (月分行事) | 坐禅会、梅花講、写経会 |
| (ほ か) | 会報、法話カードの発行 |
忌辰 録
| 八甲田山行軍兵・田中善治の碑(明治三十五年) 助産婦・主藤みわ女の碑(昭和二十八年) |
(2010年04月10日 投稿)