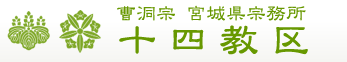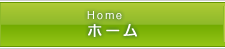当寺の前身は正長元年(一四二八年)上沼館(鶴ヶ館)主、千葉備後守の開基による。
隆池山圓福寺と称し、真言宗の古刹でありその牌所であった。
七代目千葉豊後守に至り滅亡し、圓福寺も荒廃した。その後、仙台城下、曹洞宗の松音寺・泰心院・輪王寺とともに四ヶ僧録司と称された奕葉山昌傳庵十二世意天存的和尚により寛文元年(一六六一年)再び開堂されるに至り、真言宗から曹洞宗に改宗し隆池山大龍寺と改称したとされる。隆池山の由来は寺の周囲に大小様々の池があり、寺の後方の山には樹齢二百年を数える鬱蒼とした松林を配し、前方には大きな沼があり北の松島と言われた景観を擁し、さながら龍の遊ぶ池の様であったと言われている。又寺の裏山には路地師先前家門人提歌石によって築庭された縦四十一間三尺、横二十五間四尺、石数八十三石の庭園があり、登米伊達の殿様が毎年春の花見、秋の紅葉狩りに来園されたと言われる。現況は名残りの石組みと当時植えられた目にも鮮やかな色合いをもつ紅葉が往時を偲ばせるのみである。大龍寺の現在の伽藍は十二世大忠亮順和尚の代、昭和二十七年本堂落成、十三世眞應亮雄和尚の代、昭和五十年庫裡落成、檀信徒会館は平成三年に落成したものである。又、平成九年功徳主菅原富之丞翁の発願により、大東亜戦争で戦死した戦友の供養と先祖累代先亡霊位供養のためにと鐘楼堂が寄進され、当山に梵音禅苑に響き朝暮に仏祖を供養し、濁世の人心を醒まし、迷人これによって耳を洗い菩提心を啓発して法喜禅悦の心境を開かしむるものなり。
開山以下、世代は次の通りである。
| 開山 | 意天存的 | 貞享 元年三月十一日示寂 |
| 二世 | 当陽全的 | 延寶 四年八月二十四日示寂 |
| 三世 | 一燈秀天 | 正徳 三年八月三日示寂 |
| 四世 | 然岸天廓 | 享保 七年三月三日示寂 |
| 五世 | 龜州愚鑑 | 延享 二年十月二十九日示寂 |
| 六世 | 中興丹崖道裏 | 安永 八年九月十八日示寂 |
| 七世 | 中興寶榮文山 | 文政 九年一月二十五日示寂 |
| 八世 | 古岳禅峰 | 天保 十四年三月二十八日示寂 |
| 九世 | 黙子道印 | 不明 |
| 十世 | 太林虎白 | 文久二年七月三十日示寂 |
| 十一世 | 太榮寛照 | 明治三十七年十月二十日示寂 |
| 十二世 | 中興大忠亮順 | 昭和四十四年十一月十九日示寂 |
| 十三世 | 重興眞應亮雄 | 昭和五十年三月十九日示寂 |
| 十四世 | 黙視康彦 | |
| 十五世 | 真燈道明(現住) |
(2010年04月10日 投稿)