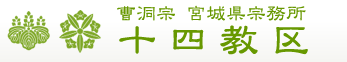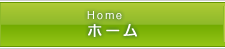当山は石越町北部に位置する、町内唯一の寺である。門前に美田が広がり、岩手県境に近い。
沿革
もともとは天台宗の寺院であった。伝説によれば、嘉祥元(八四八)年、慈覚大師が石越の地に旨江山鳳音寺台光院を開創した。そのとき、町内に柳澤寺と明道寺(あるいは祇園寺もか)、一関市花泉町油島に平等寺という支院も建ったと伝えられるが、おそらく戦国期、葛西大崎の争乱で焼亡したのであろう、みな残存せず、委細は杳として知られない。ひとり本坊の台光院のみ辛うじて残り、後世に命脈を保ちえた。即ち昌學寺の前身である。
戦国期、荒廃著しい台光院であったが、ここに黄海(一関市藤沢町)寳珠寺五世吉山松音和尚来りて錫を掛け、曹洞宗に改め、寺名を「金鷄山正覺寺」とした。弘治元(一五五五)年のことである。開基家は残念ながらわからない。
寳珠寺の住職が開いた寺ゆえ、本来は寳珠寺を本寺とするところであった。しかし察するに、石越と黄海とでは、そのあいだの北上川に阻まれて本寺末寺の往来が難儀だったのであろうか。また吉山松音和尚が、同じ寳珠寺の末寺である一関市花泉町永井・瑞昌寺にも寄留していたという深い因縁もあって、いつしか寳珠・瑞昌・昌學の三ヶ寺間で協定したのであろう。瑞昌寺を本寺としてこんにちに至っている。
また、いつ頃「石越山昌學寺」に改称したのかも詳らかではない。寺に残る「三物」(僧が師弟関係を正式に結ぶときの書類)より察すれば、およそ寛文から正徳年間(一六六一〜一七一五)にかけての改称であろうか。但し幕末の過去帳に「金鷄峯山」と記されているものもあるので、少なくとも山号は新旧併用のときが長かったのかも知れない。いずれ判然とはしていない。
開山以下、世代は次の通りである(〔 〕内は姓)。
歴代住職(示寂年月日)
| 開山 | 吉山松音 | 天正六、五、三一 示寂 |
| 二世 | 智庵宗暾 | 万治三、三、一八 示寂 |
| 三世 | 在心重暾 | 寛文一〇、八、八 示寂 |
| 四世中興 | 雪山暾英 | 宝永三、三、一三 示寂 |
| 五世 | 光山至圓 | 延享二、八、二四 示寂 |
| 六世 | 淵晟志源 | 宝暦一三、三、三 示寂 |
| 七世 | 大眠圓龍 | 明和七、一、九 示寂 |
| 八世 | 旨外達玄 | 安永九、八、三一 示寂 |
| 九世 | 本宗圓瑞 | 天明八、一〇、二三 示寂 |
| 十世 | 大愚虎關 | 文政九、八、一九 示寂 |
| 十一世 | 天雲潭龍 | 明治九、九、三 示寂 |
| 十二世 | 機宗天惠[高倉] | 明治四〇、七、一六示寂 (慶応元年胆沢郡寳壽寺に転住、同寺にて示寂) |
| 十三世中興 | 太禪龍音[菊地] | 明治六、九、一四示寂 |
| 十四世 | 祖岳龍道[佐藤] | 明治三七、一二、二七示寂 |
| 十五世 | 大心龍弘[南浦] | 大正八、二、一二示寂 |
| 十六世中興 | 大山静夫[南浦] | 昭和一六、四、二七示寂 |
| 十七世 | 梅弘仙三[柳澤] | 昭和三二、一、一九示寂 |
| 十八世重興 | 大凡浩哉[南浦] | 平成二、七、一六示寂 |
| 十九世 | 大平洋州[南浦] | 現住 |
本尊
本尊は釈迦牟尼仏。高祖承陽大師と太祖常済大師を脇侍としている。もともと、当山は延命地蔵尊を本尊としていたが、昭和三年、一関の仏師佐藤惠吉作の釈迦牟尼仏を本尊として安置し、永平寺貫首北野元峰禅師を拝請して開眼した。旧来の地蔵尊はおそらく、天台宗時代から辛くも火災をまぬがれて祀られてきた仏像のひとつであろう。以後久しく開山堂に祀っていたが、平成八年、位碑堂新築にあたってそこに遷座し、現在に至っている。
不老桜
本堂前庭にある枝垂桜。樹齢はおよそ四〇〇年と推定される。高さは十八メートル、根元の周囲は四メートルで、枝張りは東西・南北ともに十五メートルほどである。四月半ばから下旬にかけてが見頃で、先端が地面に着くほどの枝に、いくぶん濃い目の桃色の花が滝のように妍を誇る姿は圧巻であった。しかし、近年に至り樹勢次第におとろえ、東半分は完全に枯れ、残念ながら現在花をつけるのは西側四分の一ほどである。もはや往時の妍は望むべくもなくなってしまったが、目下、樹勢の回復が急務とされる。登米市文化財。
鐘楼門
間口三間、奥行二間半。胴部が上にゆくにしたがってややすぼまる「四方転び」の楼門である。天明五(一七八五)年着工、寛政九(一七九七)年竣工。町内の名匠・卯八の最後の作品である。その名の通り、戦前は二階に梵鐘がつられていたが、昭和十七年太平洋戦争激化のため供出を余儀なくされ、爾後鐘なしの鐘楼門で半世紀以上を過している。もとは茅葺で、楔を一切用いぬ造りであったが、昭和三十八年瓦葺に改造し基壇を設けた際、楔を施した。また平成十四年、老朽化した梁と一部の柱を改修した。登米市文化財。
友情碑 〜静夫和尚と仙三和尚〜
十六世南浦静夫和尚と福島県洞雲寺の柳澤仙三和尚は曹洞宗第二中学林(のちの栴檀学園)の同窓で、肝胆相照す大親友であった。それぞれ住職となってからは互いが後継住職として指名しあい、もし片方が亡くなったら残った方がその寺の後の面倒を見るという約束を交し、そう公言していた。
昭和十六年、静夫和尚は宗門の会議のため上京していた折に病を得、そのまま東京で遷化(五十四歳)。実子浩哉和尚はまだ旧制中学の生徒であった。翌十七年、仙三和尚は親友との約束を果たすために福島の寺を弟子に譲り、本務として当山住職に就任し、十八年には静夫和尚の本葬・三回忌を営弁した。師は浩哉和尚を薫陶して駒澤大学を卒えさしめ、また本堂屋根大改修を行うほか、宗門においては栴檀中学学監・学園長等を歴任し、寺の内外にわたって大きな足跡を残したが、昭和三十二年七十一歳で遷化した。
およそ一般寺院においてその後任住職は、弟子あるいは師承の系譜の近い者から選ばれるのが普通であり、この両師のように友情の絆で相続されたことはたいへん珍しいと言わねばならない。仙三和尚遷化の翌年、この友情を顕彰して師と親交厚かりし人々により、当山境内に碑が建てられた。碑に嵌めこまれたレリーフのなか、両師は互いに肩を組み、莞爾として昌學寺を見守っている。これが「友情碑」である。
(2010年04月10日 投稿)