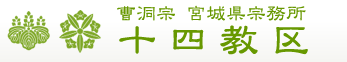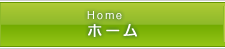当寺は法輪山大慈寺と称し宮城・岩手の県境を低く峰打つ北上山系の宮城県の北部に位置し、永享元年(一四二九年)岩手県水沢市黒石の大梅拈華山圓通正法寺四世中山良用大和尚によって曹洞宗として開創された。前身は天台宗諏訪森大慈寺と称し藤原秀衡が奥州三十三観音十四番礼所として創建された。一三五〇坪の境内には山門、本堂庫裡、鐘楼堂、秋葉大権現堂の諸堂宇が配置されているが数度の火災にあい開創以来の建物は唯一山門であろうと思われる。
正法寺には最多の時一四〇〇余の未寺があったと言われているがその中特に寺格の高い八首寺の中に入っていた。又表五ヶ院の一寺でもあり、総持寺洞川庵、輪番住職として十三世、十七世、二十一世が晋住している。
当寺には末寺四ヶ寺がある。
長松山頼光寺(三世石源興金開山)
宮城県登米市東和町米川字城ノ内 長松山頼光寺(三世石源興金開山)
宮城県登米市中田町上沼字大泉 太白山長承寺(六世花長嶽道春開山)
岩手県東磐井郡室根村津谷川 紫雲山龍洞院(七世洞室見曹開山)
岩手県東磐井郡室根村折壁 萬年山松山寺
(世泰安存道の法弟)
当寺は奥州三十三観音十四番礼所で、本尊は運慶作の聖観世音菩薩であったが現存しない。西行法師が諸国行脚中当寺を詠まれた歌が伝えられている。
頼母しや大慈の法の誓には
玉のうてなに花の白雲
と詠まれて行かれた。西行法師生誕八〇〇年を記念して昭和五十八年三月境内に歌碑が建立された。
寺宝は前にも述べたように数度の火災にあっており何一つ現存しないが安永三年三月、十七世孤峯仙巌大和尚代の書き出しによると、
一休和尚自盡自賛大黒之懸物、一幅
收渓和尚墨繪之観音懸物、一幅
弘法大師苔羅不動懸物、一幅
雪舟墨繪屏風、一双
当寺の文化財としては前述のように永享元年(一四二九年)曹洞宗として現在の地に開創された当時の建物と推定される「山門」が昭和四十七年十月十七日東和町の文化財として指定を受けている。又当寺の境内に鎮座する秋葉大権現を本尊とする「米川の水かぶり」の火伏の行事がある。この行事は起源は記録がないので定かでないが十二世紀後半藤原秀衡が天台宗諏訪森大慈寺を創建した時より毎年二月の初午の日に雲水の行として始まったものと伝えられている。雲水は行場(現在は宿と言い菅原栄氏宅)で水ごおりを取り身を清め裸になった全身に藁装束をまとい顔にかまどのススを塗り秋葉大権現に参詣し神の使いと化し町に繰り出し町の火防を祈願した。町では家々に用意された水を屋根にかけながら走り抜ける。人々は男達から藁を抜き取り屋根に上げ火伏せのお守りとする。いつごろからかわからないが当寺のお膝元である五日町の若い人も厄払いを兼ねこれに加わり現在まで一年も休むことなく受け継がれている。藁装束の一団とは別に鐘を叩く墨染めの衣の火男面と天秤に手桶を担ぐ女装のおかめの面の二人組が家々を廻り御祝儀を戴く、この御祝儀で「かさこし」と言われる参加者の慰労会が行われる。この行事は発祥以来一年もかかさず行われて来たことが認められ左記の通り文化財の指定を受けている。
昭和四十六年十月八日東和町無形民俗文化財に指定
平成三年八月三十日宮城県無形民俗文化財に指定
平成十二年十一月十七日国の無形民俗文化財の指定
この行事は五日町以外の人が入ると火災が起きるといわれ他の人を加えることはない。
当寺の教化事業、年間行事としては現況では、平成元年一月大慈寺梅花講を結成講員三十余名で定例としては月二回の練習会を行っており希望者を募って県大会、全国大会に参加している。又、春秋彼岸の中日に托鉢を行う。
歴代住職は次のとおりである
| 開山 | 中山良用大和尚 |
| 二世 | 大奇良也大和尚 |
| 三世 | 石源興金大和尚 |
| 四世 | 一天善高大和尚 |
| 五世 | 一歩宗迪大和尚 |
| 六世 | 花嶽道春大和尚 |
| 七世 | 洞室見曹大和尚 |
| 八世 | 太安存道大和尚 |
| 九世 | 一察牛頓大和尚 |
| 十世 | 玄門本的大和尚 |
| 十一世 | 天了榮眞大和尚 |
| 十二世 | 海寧高晏大和尚 |
| 十三世 | 光明一明大和尚 |
| 十四世 | 脱底知眞大和尚 |
| 十五世 | |
| 十六世 | 月鉤容輪大和尚 |
| 十七世 | 狐峯仙巖大和尚 |
| 十八世 | |
| 十九世 | 日仙孝峯大和尚 |
| 二十世 | |
| 二十一世 | 大賢哲宗大和尚 |
| 二十二世 | 蔵嶽爲霖大和尚 |
| 二十三世 | 天充獨産大和尚 |
| 二十四世 | |
| 二十五世 | 笠信峯仙大和尚 |
| 二十六世 | 欣道勵孝大和尚 |
| 二十七世 | 笠道峯夫大和尚 |
| 二十八世 | 勵學信孝 |
| 二十九世現住 | 笑歓信弘 |
(2010年04月10日 投稿)