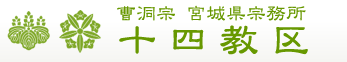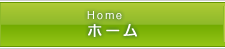所在地 登米郡東和町米川字城ノ内五番地
本 寺 東和町米川町下 法輪山 大慈寺
開 山 法輪山大慈寺三世 石源興金大和尚
長松山頼光寺は、古くは精舎山長松寺と称して天台宗であったが、鱒渕村城主及川紀伊頼家の開基となり、長松山頼光寺と改められた。この時の和尚は岩手県黒石正法寺の住職で、後に米川大慈寺三世となった石源興金和尚が開山となり、ときに永正二年(一五〇五)これより曹洞宗に改められた。寺号は鱒渕村城主及川紀伊頼家の祖先である源頼光朝臣から命名されたとも伝えられる。
本堂は間口七間奥行五間、庫裡間口四間三尺奥行七間三尺、長屋間口四間奥行二間、境内二百八十坪あり、山門は雨晴れ門、頼光寺にあり、飛騨の工匠同寺に於て雨晴しをなしたる時、其の礼として(或は左甚五郎とも言伝う)築造せしめたる釘なし組立の門なり。
一、客殿本尊 南無釈迦尊立像 寺内安置 平成四年より南無釈迦牟尼佛座像
境内には、鎮守白山権現、諏訪大明神社、天照大神宮、秋葉山大権現堂あり。
一、昭和二十二年九月 カスリン台風で檀家被害
一、昭和二十三年九月 アイオン台風で檀家城ノ内区家屋冠水四十戸
一、昭和二十五年 本堂屋根修繕
一、昭和三十一年九月 米川村錦織村合併して日高村誕生
一、昭和三十二年五月 日高村米谷町合併して東和町誕生
一、昭和三十四年 開山忌先住忌・結制
一、昭和三十八年 本堂屋根改築・開山堂
一、昭和五十八年 本堂全面改築・護持会館
昭和五十九年五月 本堂全面改築落慶法要
七月 十四教区護持会総会と研修会
一、平成二年八月 当寺護持会結成
一、平成五年 当寺庫裡新築工事 歴住・寺族墓地造成
一、平成七年七月 庫裡落慶法要 結制 歴住・寺族碑開眼供養
一、平成八年六月 梅花流宗務庁特派講習会会場(総数一〇二名)
一、平成十年七月 梅花流宗務所講習会会場(総数九〇名)
歴代住職
| 開山 | 石源興金大和尚 | 永正十五年三月七日示寂 |
| 二世 | 天巌榮普大和尚 | 天文七年八月十二日示寂 |
| 三世 | 湖渕宗珊大和尚 | 寛文十一年十二月二十五日示寂 |
| 四世 | 見亨寅【 】大和尚 | 元禄五年十月二十八日示寂 |
| 五世 | 心眼光傳大和尚 | 享保八年十一月十日示寂 |
| 六世 | 光堂元照大和尚 | 延享二年一月二十三日示寂 |
| 七世 | 月江瑞明大和尚 | 寛延三年十月十一日示寂 |
| 八世 | 観山泰音大和尚 | 安永六年八月十三日示寂 |
| 九世 | 威箭了音大和尚 | 天明八年九月十七日示寂 |
| 十世 | 大圓通音大和尚 | 天保八年四月二十五日示寂 |
| 十一世 | 逸道琳秀大和尚 | 天保十年四月三十日示寂 |
| 十二世 | 霊峰隆山大和尚 | 慶應四年三月二十五日示寂 |
| 十三世 | 竹真峰仙大和尚 | 明治二十六年三月五日示寂 |
| 十四世 | 柏樹瑞賢大和尚 | 明治三十七年八月二十八日示寂 |
| 十五世 | 普関賢孝大和尚 | 昭和十四年一月十四日示寂 |
| 十六世 | 大洞賢隆大和尚 | 昭和五十九年十月三十日示寂 |
| 十七世 | 海山宗孝 | |
| 十八世 | 瑞応賢宗(現住) |
東和町文化財 梁 川 宗 元 の 墓
梁川家は伊達家の分かれである。梁川初代の宗清は伊達稙宗(政宗の曽祖父)の八男である。伊達郡梁川城に住み、宗清には二人の子がいた。宗直、宗友である。長子宗直は政宗の命により、水沢の白石若狹守宗実の養嗣子となり宗実の死後は白石家を継ぎ伊達氏一門に入り伊達姓を賜わった。慶長四年(一五九九)十一月である。
宗清は初め男子一人だけだったので、白石家に宗直を養子にやることをしぶっていたが、政宗の命なので仕方なく承諾した。宗直に男が生まれたら、白石家を継がせて、宗直は梁川家に戻ってくることを約したのである。
宗直は慶長五年和賀忠親と南部氏との戦いにおいて、忠親に味方して南部氏と戦った。幕府に責任を問われ、宗直が自分勝手にやったこととして水沢城から登米城に移封された。その後宗清の死後、梁川家は一時断絶してしまった。
宗直は登米城主となって来てみると、天正十八年の戦で荒れ果てており町には城跡だけであったという。これの復興に全力をあげていた宗直は、ついに梁川家には帰れなかった。子供も四人になっていた。
宗直の三男又三郎宗元に梁川家を継がせることになった。梁川宗元となり東和町米谷字吉田、今の及川家前に居を構え、狼河原村(米川村)、鱒渕村(米川村鱒渕)に一四三貫文領していて、青木六反など、二股川の治水工事、その他の開発に功があったが、寛永十七年(一六四〇)二月四日三十四歳の若さで病死した。長子百助は三歳にすぎなかった。鱒渕村頼光寺境内南側の小高い丘に葬られた。
法名は頼光寺殿宝山金公大居士である。
上遠野家に再嫁した夫人、百助の母は原田甲斐の姉であった。東和町としても縁の深い人であり鱒渕の人々の願いにより、夫人の分骨が実現したのである。三四〇年ぶりに御夫妻の再会が、昭和五十九年四月十七日に実現した。現在は、頼光寺境内南側の小高い丘に、梁川宗元夫妻之墓となり管理されている。
(2010年04月10日 投稿)