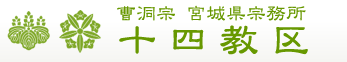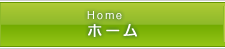当寺は、『安永風土記』書出しによれば、元徳二年(一三三〇)上野国白井雙林寺三世の開山と伝えられるが不詳。曹洞宗明峰派にして本尊は聖観世音菩薩である。その後、栗原郡高清水町龍泉寺三世一通惠最和尚(天文元年三月十五日寂)を請して開山一世とする。
龍泉寺は、永正五年(一五〇八)上州白井雙林寺四世外天守芳和尚の開山であったが、暫く無住となり福現寺の管下にあったが衰滅して卵塔場のみとなった。
文禄四年(一五九五)四月、二世山 林泰和尚代に新田十五丸に在し寺を景地の御徐地、現在地山居に移し、伊達仙台藩主大町内膳定頼公が大町縫殿家中寺として創建す。
安永九年(一七八〇)正月十四日夜大風にして本堂、庫裡、衆寮、大門等焼失、辛じて本尊及び大檀那牌を出したりと云う。
享和年間(一八〇一.〇三)十一世大梅胤光和尚代に再興し、さらに本堂は明治三十七年(一九〇四)七月、二十一世探学洞林和尚代に再建され、間口五間三尺四面であった。旧庫裡はさらに古いが建築年代不明で、間口五間奥行七間三尺、山門間口三間奥行一間三尺、山堂〈寺明細帳には妙理堂とあり〉間口三尺奥行二尺、長屋間口六間奥行二間であった。
境内地二反歩、寺有地田圃一町一反五畝歩、畑一町二反五畝歩、山林一町五反三畝歩を有す。昭和二十四年本堂茅葺き屋根をスレートに葺き替え。
昭和四十六年六月庫裡間口九間奥行五間(新築)
昭和五十一年十一月鐘楼堂間口二間四面
昭和五十五年七月檀信徒会館間口七間奥行五間
昭和六十三年十二月接賓間口四間三尺奥行三間
四尺、境内整備
平成二年七月駐車場造成(墓地前)
平成四年八月駐車場鋪装工事
平成九年六月開山堂、位牌堂間口四間奥行五間
平成十五年六月 二十四世大法宗林和尚十三回忌に伴い、墓地前参道付替へ北側参道(御坂階段取付)整備予定。
逐次、修復整備を重ね嘗って見ざりし輪奐の美を表し、爾来、地域における仏信徒の中心的祖先の菩提所として尊崇を聚め崇仏報恩の精神に基き護持せらる。
大町氏は、清和天皇六代の孫、経基の末葉山田兵庫介忠家の次男助経、十郎とも称し従五位下筑後守、姓は源、母は小椋左馬介源孝綱の女、建長六年三月筑後国三毛郡(三池郡)において、五〇〇〇貫文を領し、同郡大町の庄に住したことから大町を称したのに始まる。
助経十六代義頼(幼名千熊また駿河とも称せらる)は、伊達氏に属し、天正十三年十一月人取橋の戦いに十五歳で出陣、その後諸処に転戦し軍功により、政宗公その胆力を賞し、源四郎と名を賜う。
新田大町氏初代、内膳定頼は義頼の次男、母は刑部清水監物信澄の女である。初め父義頼の遺領二〇貫文を分け賜る、寛永五年五月兄通頼采地を没収されたその内から三〇貫文加賜され、一族の座を許される。同十五年通頼の赦免に伴い、定頼は、兄通頼に座を譲らんことを請う、忠宗その節に感じこれを許し、別に着座を仰せつけらる。
忠宗時代に胆沢郡下姉体村に新地十五貫三三四文、さらに十三貫六六文を加賜された。
寛永二十一年八月十四日采地高八十七貫五百五十八文の御判物を賜わる。
萬治二年隠居
寛文四年十月十日卒 年六十七歳
法名 清室寒江 墓碑 新田姥沢
追号 慈眼院殿清室寒江大居士 位牌 慈眼寺納
歴代住職(示寂年月日)
| 開山 | 一通惠最大和尚 | 元徳二年二月十二日 天文元年三月十五日不詳 |
| 二世 | 山林泰大和尚 | 文亀二年二月十三日 |
| 三世 | 照巖俊泰大和尚 | 天文元年三月十五日 |
| 四世 | 露巖亮鶴大和尚 | 天正四年四月十五日 |
| 五世 | 一峯頓超大和尚 | 寛文元年九月十七日 |
| 六世 | 長列 天大和尚 | 亨保十五年九月二十三日 |
| 七世 | 中興梁渕俊棟大和尚 | 宝暦二年 二月五日 |
| 八世 | 得外泰髄大和尚 | 明和元年 不 明 |
| 九世 | 鐡巖寂如大和尚 | 安永八年十一月七日 |
| 十世 | 泰堂魯英大和尚 | 天明二年 四月七日 |
| 十一世 | 大梅胤光大和尚 | 寛政四年 二月七日 |
| 十二世 | 海岩實音大和尚 | 文政十年四月十二日 |
| 十三世 | 凌雲巨岳大和尚 | 文政十年 五月五日 |
| 十四世 | 千山大龍大和尚 | 天保二年十月十九日 |
| 十五世 | 慈道良愛大和尚 | 不 明 |
| 十六世 | 天冲美猊大和尚 | 不 明 |
| 十七世 | 逸山俊芳大和尚 | 不 明 |
| 十八世 | 融山孝道大和尚 | 弘化四年 六月一日 |
| 十九世 | 大眞寛良大和尚 | 嘉永五年十一月二十八日 |
| 二十世 | 智戒洞順大和尚 | 明治二十四年正月十四日 |
| 二十一世 | 探學洞林大和尚 | 昭和十七年七月二十六日 |
| 二十二世 | 徳山壽雄大和尚 | 昭和十八年海蔵寺より晋住 昭和二十二年海蔵寺へ転住 平成十三年十月十八日 |
| 二十三世 | 大法宗林大和尚 | 平成三年 六月三日 |
| 二十四世 | 大仙修光 現住 | 昭和五十八年九月十二日就任 |
涅槃図 安政三辰年二月十四日 十九世 大眞寛良代
(2010年04月10日 投稿)