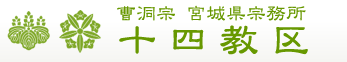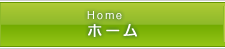一、冷松寺の沿革
1 冷松寺の前身
冷松寺は、元、室町幕府管領家斯波氏の先祖、足利家氏の菩提所として延元2(1337)年、その居住地総州大崎の荘(現千葉県佐倉市辺り)に開創され、当寺は天台宗雙元寺と称した。家氏の孫、斯波家兼(奥州大崎氏祖)は、足利尊氏の命を受け奥州探題として文和3(1354)年、奥州に下向、寺もそれに従い黒川郡大崎の地(現黒川郡或いは古川市)に移転したと言う。さらに、大崎氏七代教兼(法名龍谷院殿)の代、康正元(1455)年、上州白井(現群馬県北群馬郡)雙林寺三世曇英慧應和尚を開山に請し、曹洞宗に改宗し、鳳凰山龍谷院と改称したと言う。しかしながら以上の事は伝承に由るもので確かな記録は現存しない。
2 冷松寺と改称
天正18(1590)年、豊臣秀吉の奥州仕置により大崎氏は滅亡するが、大崎氏五代満詮の弟、大崎持家を祖とする一族の高泉氏四代高景(法名冷松院殿 栗原郡高清水に住す)は、一時身を潜めるも、文禄元(1592)年、伊達政宗の家臣(準一家)となり、栗原郡太田村(現築館町)に二十貫文(二百石)を賜ると共に、大崎氏の菩提所を再興し、鳳凰山冷松寺と改称し、高泉氏の菩提所とした。由って冷松寺の開基(中興)を高泉高景、時の六世総芝守統和尚を中興開山としているのである。
尚、昭和49年、築館町にあった高景の墓石を冷松寺裏山の高泉氏廟所に移している。
高泉氏五代定康の代、寛永年中、登米郡黒沼村(現中田町黒沼)への移封と共に冷松寺も移転、さらに高泉氏六代兼康の代、元禄17(1704)年、登米郡米谷村(現東和町米谷)に移封、冷松寺も又同地に移転し、現在に至っている。
移転前は、柴田家菩提所日蓮宗蓮華寺があり、その時代に建てられた墓碑数基が本堂後方に現在も残っている。高泉氏はしばしばの加封により三千石を賜るが、その加封と共に冷松寺も七堂伽藍完備し、常在の雲水(修行)僧三十人を有し、北上河畔一大霊場の観があったと言う。
3 現在の冷松寺
冷松寺の伽藍は、米谷移転以来、修繕を加えつつ維持してきたが、老朽化も進み、遂に二十六世大光得玄和尚の代に至り、住職、檀信徒一大発願して共に力を合わせ、昭和55年本堂落成、続いて平成元年庫裡並びに檀信徒会館の落成に至る。往時の盛大には及ばぬものの、今後の時代の信仰の場、布教の場としての整備がなされたのである。
二、歴代住職 ※( )内は示寂年月日
| 開山 | 曇英慧應(1504年10月14日) |
| 二世 | 操芝正旭(1523年11月13日) |
| 三世 | 太初全甫(1534年10月15日) |
| 四世 | 明巌詞哲(1570年 4月15日) |
| 五世 | 天仲全育(1588年 3月 5日) |
| 六世 | 中興 総芝守統(1603年 1月 9日) |
| 七世 | 來菴長從(1619年 8月18日) |
| 八世 | 輝総壽暾(1676年12月 5日) |
| 九世 | 吟菴全龍(1708年 9月 2日) |
| 十世 | 龍山智門(1718年10月15日)※泰心院(仙台市)へ転住 |
| 十一世 | 學海珍禅(1718年10月 6日) |
| 十二世 | 大道玉隣(1723年 4月17日) |
| 十三世 | 大蟲祖徹(1756年 2月19日) |
| 十四世 | 鐵門玄髄(1767年 9月15日)※西福寺(色麻町)より出頭 ※報恩寺(中田町)へ転住 |
| 十五世 | 日山亮海(1763年10月 3日) |
| 十六世 | 天外物先(1773年11月 4日)※洞雲寺(千厩町)より出頭 |
| 十七世 | 雲源得苗(1803年12月29日)※永伝寺(富山県)へ転住 |
| 十八世 | 石堂班牛(1817年11月12日)※永伝寺(富山県)へ転住 |
| 十九世 | 東海冨山(1799年11月22日)※円満寺(一関市)へ転住 |
| 二十世 | 玉斧丹桂(1815年 1月14日) |
| 二十一世 | 物外象先(1828年 1月26日)※光明寺(中田町)より出頭 |
| 二十二世 | 中興 徳想徳本(1862年 9月 3日) |
| 二十三世 | 穆本歓全(1903年 3月21日) |
| 二十四世 | 歓慶徳真(1944年 6月15日)※普慶院(東和町)より転住 |
| 二十五世 | 文山徳明(1950年 6月 8日) |
| 二十六世 | 大光得玄(2003年退任 現東堂) |
| 二十七世 | 梅輝俊二 現住職 |
三、本寺雙林寺
冷松寺の本寺は群馬県北群馬郡子持村の最大山雙林寺である。寺域約三千坪、堂塔十三を数え、文安4(1447)年5月、白井城主長尾景仲の開基、通幻派月江正文禅師の開山として開創された関東の名刹である。後に輪住制の執行により、大本山總持寺、本寺最乗寺(神奈川県)の輪番住職を数多く勤め、曹洞一派の振興に尽くした。末寺48ケ寺を始め門葉末派は863ケ寺を数えている。
四、冷松寺の末寺六ケ寺
東渓寺(遠田郡田尻町)三世太初全甫和尚開山※現在末寺九ケ寺、孫末寺一ケ寺
広禅寺(古川市師山)四世明巌詞哲和尚開山※現在末寺二ケ寺、孫末寺一ケ寺
宗松寺(岩手県東磐井郡東山町)六世総芝守統和尚開山※現在末寺一ケ寺
西福寺(加美郡色麻町)六世総芝守統和尚開山※現在末寺二ケ寺
保昌寺(登米郡中田町)七世來菴長從和尚開山
虎渓寺(栗原郡瀬峰町)七世來菴長從和尚開山
(2010年04月10日 投稿)