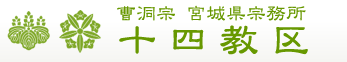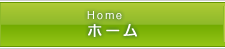一、所在
中田町浅水長谷山三六四
長谷山(水越山とも言う)は北上川の西岸に位置し東和町の米谷山と相対している標高五一、三メートルの館址である。
長谷山を切り割りした一関、津山を結ぶ国道三四二号を横断し高い石段を登りきった所に本堂が位置する。
本堂西北眼下真下に、慶長十年(一六〇五年)登米城主、伊達相模宗直公の掘さくと伝えられる相模土手に守られる奥州北上川が豊かに流れる。
今こそ堤防決壊による水害の惨事より守られた美田が広がるはるか彼方に栗駒山をいただき、北上川に落つる太陽は光々と光明寺を照らす。
二、由緒
光明寺の法系は峨山禅師の門下二十五哲の一人大源宗真である。愛知県性海寺開山、周鼎中易よりその法を中田の地に流布、登米町 龍源寺に至る。同寺五世 明巖 哲(慶長十四年八月二十四日遷化)開山、現在に至る。
照谷山光明禅寺御開山法系
○高祖承陽大師―孤雲懐弉禅師―徹通義介禅師―太祖常済大師―我山紹碩―大源宗真―梅山聞本―恕仲天 ―真岩道空―川僧恵済―逆翁宗順―芝岡宗由―周鼎中易―禅室珠悦―胡山省鑑―龍源開山天以乾済―法菴玄器―中室存的―観空周應―当寺開山明巖 哲大和尚禅師
開山 天正十二年六月(一五八四年)
本寺 登米町龍源寺
本尊 釈迦牟尼仏
三、本尊、仏像、諸堂
本尊 釈迦牟尼仏
奉建立 天明三年四月七日(一七八三年)
施主 水越村 荒神堂 清太郎
同本堂須弥壇 及び前机
寛政元年五月十一日(一七八九年)
施主 当村 清太郎
脇仏 文殊菩薩 普賢菩薩
寺宝として天平年間(七二八.七八四年)作と伝えられる地蔵尊仏体があり千体仏の一つと伝えられる。
本堂 間口七間一尺 奥行六間一尺
庫裏(五七坪)昭和四十六年十二月建築 昭和五十五年本堂内陣改修
四 、歴代住職
| 開山 | 【】明巖 哲大和尚 | 慶長十四年八月二十四日示寂 |
| 二世 | 雪巖全達大和尚 | |
| 三世 | 行巖【】達大和尚 | |
| 四世 | 貴山萬達大和尚 | |
| 五世 | 行山圓住大和尚 | |
| 六世 | 珠嶽順光大和尚 | |
| 七世 | 曹水儀源大和尚 | |
| 八世 | 順應萬瑞大和尚 | 宝暦十年十一月二十八日示寂 |
| 九世 | 大州常輪大和尚 | 天明四年九月六日示寂 |
| 十世 | 雲龍雷峰大和尚 | |
| 十一世 | 善峰榮積大和尚 | |
| 十二世 | 物外象光大和尚 | |
| 十三世 | 要山梅玄大和尚 | |
| 十四世 | 祖印提宗大和尚 | |
| 十五世 | 慧穏瑞明大和尚 | 文久元年一月十三日示寂 |
| 十六世 | 中興禅翁善山大和尚 | 明治十九年十二月二日示寂 |
| 十七世 | 東海越龍大和尚 | 明治三十一年四月十九日示寂 |
| 十八世 | 中興佛光隆童大和尚 | 昭和十七年四月十九日示寂 |
| 十九世 | 壽山憲隆高和尚 | 昭和二十四年二月十九日示寂 |
| 二十世 | 法海一舟大和尚 | 昭和五十四年八月十二日示寂 |
| 二十一世 | 中興正倫介立大和尚 | 平成四年八月二十八日示寂 |
(2010年04月10日 投稿)